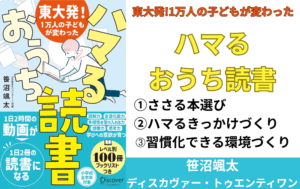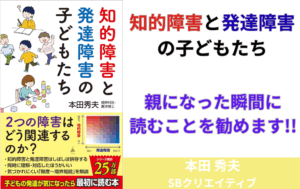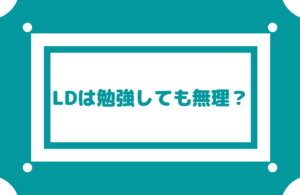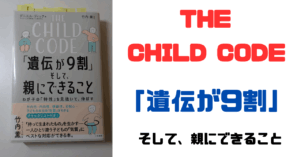苫野一徳先生の『勉強するのは何のため』を久しぶりに読み直し
やっぱりこれは多くの人に読んでもらいたいと紹介することにしました。
目次
『勉強するのは何のため』
私が苫野先生を知るきっかけになったのが『勉強するのは何のため』です。
なぜ勉強をするのか?
定期テストのためだけの暗記、受験以外では役に立たない知識の暗記
勉強ができるだけでは生きていけないのは分かり切っているのに・・・
子供たちが学校で学んでいることに意味はあるの?
かといって、学歴がなくてもいいのか・・・
結局、子供たちに何をさせることがいいのか
こういう迷い、不安をかかえている方には何かしら得るものがあるはずです。
私は『勉強するのは何のため』を読むことで
頭の中でごちゃごちゃして言語化できないもやもやが少し晴れました。
本を読んだからといって教育の正解は見つかりませんが、
自分にとっての正解をみつけるきっかけになると思います。
自分なりの答えを探す
「勉強しなさい」と言わなくても勉強をすることが当たり前の環境を普段の生活で作れたとしても
一定の年齢に達すれば「勉強をする理由は何?」と多くの子が疑問に思うはずです。
これに対する自分なりの答えをちゃんと話せるようになっておくことは大切だと思います。
「なんで勉強をしなくちゃいけないの?」
と子供に問われ
「テストで点数を取るため」「受験に必要」「大人になるために必要」といった返事しかできないようでは危険です。
子どもが完全に納得できる返事をするのは無理かもしれませんが、「ちゃんと考えているんだ」と子供が感じてくれれば、少なくとも勉強を全くしないでダラダラするというようなことは避けられるはずです。
自分なりの勉強をする理由を考えるには、上に紹介した本だけでなく、できれば『教育の力』より深く考える場合は『どのような教育が「よい」教育か』を読んむことを勧めます。
「どのような~」は内容がかなり難しいですが、『勉強するのは何のため』『教育の力』の2冊を読んだ後是非読んでください。
これらを読めば
「自分が過去に受けた教育が本当に正しかったのか?」
「今の子供たちはどういう学びが必要なのか?」
といったことにたいする自分なりの考えをしっかりと持てるようになります。
哲学
2014年ころになりますが、はじめて『どのような教育が「よい」教育』を読んだときは、正直、何が書かれているかあまりわかりませんでした。
そこに、最低限の哲学・思想の知識が必要だったからです。
「こんなに難しい本があるんだ」という衝撃(現代文をまじめに勉強しなかったことが原因)から、「この本を読めるようになりたい」という気持ちが湧き出てきました。
これが、私が哲学・思想、そして現代文の重要性に気づくきっかけです。
私が現代文が大切だと思うようになってから実は結構日が浅いんです。
もし、上で紹介した本を読んで少しでも哲学に関心を持ってもらえたら
『はじめての哲学的思考』を勧めます。
中学生でも読めるように書かれてあるので、哲学がどういうものなのかを無理なく知ることが出来るはずです。