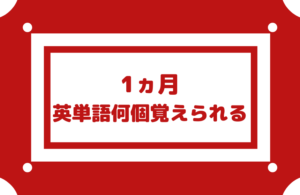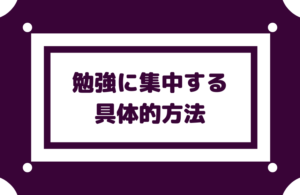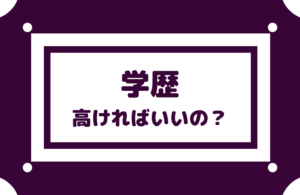中学1年の時にどれだけ勉強をしても勉強ができなかったのに、中学3年になるころには普通にできるようになる。
中学1年の時は英単語の暗記に相当苦労をしていたのに、中2になるころには少しずつ覚えられるようになる。
勉強が出来なかった原因が、認知的なことが原因でないのであればこういうことは起こり得ると思います。
目次
学校の勉強に興味がない
親から無理やり勉強をさられている子の中には、勉強時間に見合うだけの結果が出せない子もいるはずです。
もちろん結果がでないことだけを見れば
理解力がない、認知的なことが原因で英語のアルファベットが覚えられなかったり、漢字の暗記が苦手な可能性、その他学習に何らかの困難を抱えている可能性考えられます。
しかし、認知機能が原因でない可能性も十分考えられます。
勉強以外で興味のあることはものすごい記憶力があるのに、学校の勉強(興味のないこと)になると本当にまったく何も覚えられない子がいるらしいのです。
国語はできるのに、他の科目は全くできない。
英語、乃至、数学だけはできるが、他の科目は平均以下。
英語・数学はどれだけ授業を聞いても何も理解できない、逆に、社会・理科だけはそこそこの点数が取れる。
こういうことが普通にあります。
なので、「理科・社会の成績が極端に悪い」というだけで勝手に「学習障害なのかも」、と決めつけることはできないのです(この手の検索は本当に多い)。
このような子たちの中には勉強に関心を持ち始めたら一気に成績が伸びることもあります(頭が異常に良い人の中にこの手の人が少なからずいると私は思っています)。
このような状況にある場合、嫌がっている科目を無理に勉強をさせるよりも、できる科目だけ伸ばしてあげる(できない科目があってもできる科目があればいいという気持ちを持つ)方が、親子ともに心理的に不安定にならないと思います。
やる気がない
「勉強をしているのにできない」という経験を繰り返したことで、やる気がなくなっている可能性もあります(学習性無力感)。
勉強ができない子の親の中には「やればできるのに、やる気がないからできない」と思っている方が相当数いると思います。
確かに、本当にやっていないことが原因の場合もあります。
事実、私は小学校の時の漢字のテストで0点を取っていましたが、それは漢字は暗記が必要だからです。
暗記をしなければ漢字が書けるわけがないので0点を取るのは当然です。
社会・理科も学校の授業を聞いていませんし、国語に関しても言葉を知らないので文章を読めるわけがありません(今思い返すと、文章が読めなかったのではなく文章を読んでいなかったのだと思う)。
私が、小学校のテストで70点未満しか取れない状況なのは明らかに勉強不足が原因でした。
中学1年の最初の実力テストでなにも勉強をしていないのになぜか平均点を超えた(小学校のテストで点数を取れていなかったのになぜ中学の実力テストで平均を超えたのかは分からない)ことからも、勉強不足が原因で勉強ができなかったのは明らかです。
しかし、私のように単に勉強不足ではない場合も否定できないので「やる気がない」原因が本当に単に「勉強をしたくない」からなのかを見極める必要があると思います。
集中力がない
勉強ができない原因が集中力がないことが原因なこともあります(嫌いな科目だけ集中力がないということもあります)
集中力がない子に「1時間勉強しなさい」「家に帰ってきたらずっと勉強しなさい」などと言っても何も意味がありません。
親に反発する子は親の言葉を無視するでしょうし、親に反発できない子は自分の部屋に引きこもって勉強をしたフリをするでしょう。
集中力のない子には集中して勉強をさせる工夫をする必要があります。
たとえば、時間単位で勉強をさせるよりも「このページをやる」「漢字プリントの漢字を1枚全部覚えるだけでいい」など、です。
終わりが見えるノルマを与える方が集中して勉強に向かう可能性が高いです。
ここで大切なのは、1ページでも構わないから、漢字1個でも構わないから、行動に移させることです。
欲張って多くのことを要求してしまえば、何もやらなくなります。
もちろん、ノルマを極限まで絞ったとしても、やらない子がいると思います。
どれだけ言っても1分も勉強をしない場合は、勉強をやる時期ではないと諦めてください。
仮にその時はやらなかったとしても、親が子供に勉強をしてもらいたいという雰囲気(怒りではなく期待)を出していれば子供はそれを感じ取ります。
小学校の時に全くやらなかった子が中学生になりやり始めたり、中学1・2年のときは勉強時間ゼロだったのに中学3年になったら急にやり始めることもあります。
受験が近づいている親からすれば「そんな悠長なことは言ってられない」と思うでしょう。
しかし、本人の意思を完全に無視して勉強をさせて中学受験・高校受験に成功したとしても(中学受験は嫌々ながらだと成功しませんが)、結果的に燃え尽きて終わったり、親への反発心が膨らむかもしれません。
もちろん、結果的に良い方向に向かう可能性も否定はできませんが。
「できる範囲で、少しずつ」で、親が辛抱し、本人が気づくのを待つことを私は勧めます。
怒るのではなく期待しているという声掛けが大切です。
やってもできない場合もある
勉強を必死に頑張ったとしても
なかなか思うように成績を伸ばせないことはあります。
普通の塾講師は思うように成績が伸びない子に
「頑張れば誰でも成績が伸びる、伸びないのは勉強のやり方が間違っているからだ」
というはずです。
ただ、残念ですが、スポーツに向き不向きがあるように勉強にも向き不向きがあります
どれだけ必死に頑張っても努力に見合う結果が出ないことは絶対にあります。
これは塾講師としていろいろなタイプの子を見てきているなら絶対に気づくことです。
講師になって日が浅かったり、入塾テストでふるいにかけできる子しか集まっていないクラスしか教えたことがなかったりすると気づくことがないかもしれませんが
長年色々な学力が集まる子供たちに授業をしている塾講師が
授業中に子供たちの表情を見て
理解しているか、集中しているか、暗記がどれくらいできているか
普段の勉強のやり方を間違えていないか
といったことを注意して見ていれば、
努力不足が原因で思うような結果が出せないかどうかは確実に分かります(場合によっては1度の体験授業でもそれとなく分かってしまうこともあります)。
そういうことがあるにもかかわらず
入塾前にその点に一切触れず他の塾で成績が伸びなかった
必死に頑張っているのに平均点も取れない
という子に対し
「それはその塾の教え方に問題があるから。成績が伸びないのは努力の問題、やり方の問題なだけだからうちの塾に入れば絶対に成績は伸びる」
なんて言う方
私は残酷だと思います。
それで結果成績が伸びなかったら
塾のせいではなく本人のやり方や努力に問題があるというのでしょうか?
仮に自分が本気で頑張っても結果が出せない状況にいる子だとして
親からは激怒され
塾では努力していないだけと自分のせいにされる
考えただけでも私には耐えられません。
だから何かと言われたら何を言いたいのかはわかりませんが
必死に頑張っているのに結果が悪いと、その結果だけを見て、なぜその結果になっているのかを確認することもなしにただ怒るだけの親
必死になっているのに成績が伸びない子に、「努力していないだけ」と向き合いもしない塾講師。
そうあってはならないとは思います(もちろん、中には向き合おうとしても向き合えない親・子がいるのは分かっています。だから、「頑張れば誰でも絶対にできるようになる」なんて平気で言ってしまう塾講師が少なからずでてきてしまうのかもしれません)。